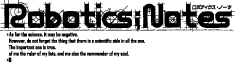Special
Interview2
![]()
――今回の『ROBOTICS;NOTES』は、野村監督の前作『戦国BASARA弐』とは同じゲーム原作とはいえ、まったく趣きが異なる作品ですね。
野村 ちょうど『戦国BASARA弐』の作業が終わった頃に、(アニメーション)プロデューサーの松下さんから、今回の監督のお話を―『ROBOTICS;NOTES』をゲームの制作とほぼ同時進行で、アニメ化したいというお話をいただいたんです。今回は原作がアドベンチャーゲームということもあるし、なにより高校生たちの日常生活がメイン。僕自身、現実に近い世界が舞台になる作品は、今回がほぼ初めてなんです。
――武将たちがチャンバラする世界とは正反対ですよね(笑)。
野村 はい(笑)。『電脳コイル』は小学生が主人公でしたし、『戦国BASARA弐』は、ほぼファンタジーみたいなアクション物でしたから。ただ、こういう作品をずっとやってみたいと思っていたので、念願叶ったというところはあります。自分が実生活で得た経験値みたいなものを、そのまま反映できる。もちろん難しいところもいっぱいあるんですけど……。
――今回、原作をアニメ化するにあたって、特に気をつけなければならなかったところはありましたか?
野村 "原作に出てくる要素はなるべく取り込む"というのが、まず大前提としてありました。あとゲームだと、エピソードに合わせて主観となるキャラクターが変わるんですよね。主人公は海翔ということになっているのですが、ときにはあき穂の目線になったり、淳和の目線になったりする。でも、それをアニメーションでやるのは、非常に難しい。誰かひとりに焦点を絞って、その人の主観でストーリーを追いかけていく……というやり方をしないと、たぶんいろいろと破綻するな、と。そこで最終的にはほぼ海翔に主観を集約させて、見せていこうと考えました。
――比較的、リアルな日常芝居が基本の作品になっていますよね。
野村 そうですね。とはいえ、完全にリアルにしてしまうと、どんどん物語が狭苦しくなってしまう。アニメーションでやる必要がなくなってしまう気がしたので、コミカルな場面は思い切りコミカルに、アニメっぽく演出しています。誇張するところは、キチンと誇張しよう、と。ただそこのバランスというのは、ぼくのさじ加減ひとつだったりするので、結構、難しいところなんですが。
――じつは第1話を拝見していて、一番驚いたのは、あき穂のデフォルメ顔でした(笑)。「ああ、こういう方向もアリ」にするんだな、と思ったのですが……。
野村 じつはそれも、キチッとルール化しているわけではないんです。久保田(誓)さんのキャラクターデザインにも、ギャグ顔は一切ない。基本的に、原作のデザインをアニメ的に表現するにはどうすればいいかを考えて、ちょっとリアル寄りにデザインを起こしてもらっています。で、演出する際にそこを崩そうと。といっても僕たちが独断でやっているわけではなくて、原作のキャラクターデザインを拝見したときに、わりと崩した表情が多かったんですよ。なので"ここまでやっていい作品なんだな"という認識があったので、それを取り入れちゃおう、というのはありました。
――日常の芝居のなかに、ああいうギャグ顔がスッと入ってくることで、ある種のテンポ感が出ているのかな、と感じました。
野村 そこはすごく気を遣いました。僕ら自身、日常の会話とかやり取りのなかで、完全にリアルな立ち居振る舞いしかしないかというと、そんなことはないと思うんですよ。擬音だって喋るし、ノリツッコミだってする。まずなによりキャラクターの個性をしっかり見せたい、というのがあったので、それを表現するうえで必要なことは積極的にやっていきたいな、と。


――あと種子島らしい、鮮やかな美術も魅力のひとつです。監督はロケハンに行かれたそうですね。
野村 去年の10月頃ですね。3泊4日くらいでお伺いしたんですが、最初の印象は"人がいないな"と(笑)。街中を歩いてる人がいなくて、基本、車での移動がメインなんだ、と。劇中でも海翔たちが乗ってますけど、学生はバイクなんですよね。ストーリーの展開上、海翔たちは東京に行くことになるんですけど、東京は人がいっぱいいて、明かりも多い、けれども種子島では歩いている人がいない……みたいな、ギャップが出せればいいのかな、と。
――『ROBOTICS;NOTES』は、タイトルにも出てくる通り、ロボット物の側面もありますよね。監督はこれまで、ロボットアニメを手がけられたことは……。
野村 ないです。もちろん観たことはありますし、前々からやってみたいとは思っていたんですけど、『ROBOTICS;NOTES』について言えば、原作がロボット物だと聞いて"こういう雰囲気なのかな"って想像していたものとは、まったく違った(笑)。なにせ、最初にいただいたロボットのデザインが、ガンつく1とガンつく2でしたからね。"これかー!"ってド肝を抜かれたんですけど(笑)、じつはストーリーにちゃんと沿ったデザインになってる。基本的に一番描きたいのは、キャラクターのお芝居なんですけれども、そこには巨大な鉄の塊であるロボットもいて、そのリアルさも描ければな、と。
――もう少し詳しく、お聞かせいただけますか?
野村 あき穂にとってガンつく1は、感情がある存在なんですよ。ただ乗り込んで、敵を倒せばおしまい、というようなモノじゃない。きちんと触れたり、話しかける相手なんです。もちろん話の途中まではあき穂自身、それほど技術があるわけじゃないので、せいぜい油を差したり、磨く程度のことしかできない。でも、いざガンつく1を完成させようと思い始めてからは、可能な限り、組み立てに関する絵作りをしっかりやりたいな、と。"これだけ巨大なモノを組み立てるには、こういう工具も必要だろうな"とか、無い知恵を絞っていろいろ調べながら絵作りをしよう、というのは考えました。
――キャラクターのお芝居が中心になるというお話ですが、監督が気に入っているキャラクターは?
野村 ほかのインタビューでは、長深田一族が好きだという話をしてるんですけど……(笑)。一番自分の高校時代に近いのは、海翔ですかね。海翔って、基本的にゲームにしか興味がないんですよね。ロボット作りにも興味がないし、フラウが使うネットスラングもわからない。そういうところが、僕に似てるかなあ、と。僕も高校時代はすごくゲームにハマってて、逆に言えば、興味のあることしかやらなかった。だから、海翔の気持ちはすごくわかる部分がある。
――ただ、彼の性格ってすごくクセがありますよね。
野村 クセは強いですよね。ぼくも最初、原作のシナリオ読んだときには"すごくイヤなヤツだな"と思いましたし(笑)。興味のないことに関してはすごくフラットなんだけど、いざ興味が出てくると、スイッチが入る。根はいい人だけれども、その部分は周りからは分かりにくいんですよね。僕自身もよく他人から"飄々としている"と言われたりするので(笑)、その微妙なさじ加減というかバランスが取りやすいかなあ、と。あと声だけで言えば、細谷(佳正)さんにやっていただいてる昴とか、君島コウ役の森川智之さんですかね。わりと渋い声が好きなので、聞いてるだけでシビれてしまうというか(笑)。森川さんとは『戦国BASARA弐』でもご一緒したんですが、あの低音には聞き惚れちゃいますね、やっぱり。